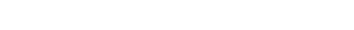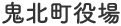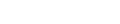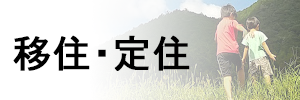本文
文化財
文化財
指定文化財目録 (令和7年3月10日現在)
| 番号 | 指定 区分 |
名称 | 所在地 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国有 | 善光寺薬師堂附厨子 | 小松 | 昭和52年6月27日 |
| 2 | 国民 | 伊予神楽 | 内深田 | 昭和56年1月21日 |
| 3 | 国記 | 等妙寺旧境内 | 芝・中野川 | 平成20年3月28日 |
| 4 | 国登 | 鬼北町庁舎 | 近永 | 平成24年2月24日 |
| 5 | 国登 | 井谷家住宅 主屋 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 6 | 国登 | 井谷家住宅 蔵 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 7 | 国登 | 井谷家住宅 石垣及び土塀 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 8 | 国登 | 井谷家住宅 南面石垣 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 9 | 国登 | 井谷家住宅 給水用隧道 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 10 | 国登 | 明星草庵 | 下鍵山 | 平成24年8月13日 |
| 11 | 県有 | 木造菩薩坐像(伝如意輪観音像) 等妙寺 | 芝 | 平成19年2月20日 |
| 12 | 県有 | 鬼北文楽人形頭・衣裳道具一式 | 出目 | 昭和34年3月31日 |
| 13 | 県民 | 清水の五つ鹿踊り | 清水 | 昭和40年4月2日 |
| 14 | 県記 | イトザクラ及びエドヒガン | 内深田 | 昭和24年9月17日 |
| 15 | 県記 | 岩谷遺跡 | 岩谷 | 昭和57年3月19日 |
| 16 | 町有 | 等妙寺観音堂附厨子 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 17 | 町有 | 等妙寺山門 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 18 | 町有 | 等妙寺鐘楼 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 19 | 町有 | 等妙寺蔵宮殿(くうでん) | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 20 | 町有 | 逆修塔・宝篋印塔 円通山善福寺跡 | 川上 | 平成7年2月27日 |
| 21 | 町有 | 庚申塔及び慶長の石碑 常願寺 | 吉波 | 昭和52年10月28日 |
| 22 | 町有 | 義農武左衛門顕彰碑 | 下鍵山 | 昭和55年11月5日 |
| 23 | 町有 | 木造薬師如来坐像及び二天十二神将 善光寺 | 小松 | 昭和52年10月28日 |
| 24 | 町有 | 木造阿弥陀如来坐像 善光寺 | 小松 | 平成29年3月28日 |
| 25 | 町有 | 木造毘沙門天及び不動明王立像 等妙寺 | 芝 | 昭和52年10月28日 |
| 26 | 町有 | 木造僧形神坐像(十禅師権現像) 等妙寺 | 芝 | 令和2年3月28日 |
| 27 | 町有 | 木造釈迦如来坐像 龍渕寺 | 上川 | 昭和52年10月28日 |
| 28 | 町有 | 木造虎関師錬倚像 龍渕寺 | 上川 | 昭和52年10月28日 |
| 29 | 町有 | 木造千手観音坐像 宝樹寺 | 柏田 | 昭和52年10月28日 |
| 30 | 町有 | 木造千手観音立像 普門山観音寺 | 西野々 | 平成7年2月27日 |
| 31 | 町有 | 木造阿弥陀如来坐像 大安山禅定寺 | 広見 | 平成7年2月27日 |
| 32 | 町有 | 木造如意輪観音坐像 等善寺 | 東仲 | 平成30年1月23日 |
| 33 | 町有 | 絹本著色両界曼荼羅 等妙寺 | 芝 | 昭和52年10月28日 |
| 34 | 町有 | 絹本著色如意輪観音像 | 芝 | 平成18年2月22日 |
| 35 | 町有 | 絹本著色不動明王及び二童子像 | 芝 | 平成18年2月22日 |
| 36 | 町有 | 絹本著色授戒本尊 | 芝 | 平成12年3月31日 |
| 37 | 町有 | 絹本著色釈迦三尊十六善神像 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 38 | 町有 | 絹本著色慈恵大師像 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 39 | 町有 | 紙本墨画淡彩地蔵菩薩像及び二童子像 | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 40 | 町有 | 初代国正大本神社奉納の大太刀附白鞘 | 内深田 | 平成22年3月25日 |
| 41 | 町有 | 一の宮大明神経筒 | 近永 | 平成7年2月27日 |
| 42 | 町有 | 書本大般若経 吉蔵寺 | 沢松 | 昭和52年10月28日 |
| 43 | 町有 | 奉公明伝集 | 清水 | 平成7年2月27日 |
| 44 | 町有 | 井谷家所蔵資料 | 下鍵山 | 平成25年3月26日 |
| 45 | 町有 | 成藤新田神社棟札 | 成藤 | 平成7年2月27日 |
| 46 | 町有 | 広見大本神社棟札 | 広見 | 平成7年2月27日 |
| 47 | 町有 | 天満大自在天神宮棟札 白王神社 | 延川 | 平成7年2月27日 |
| 48 | 町有 | 鳳凰山成杖寺六導図 | 内深田 | 平成7年2月27日 |
| 49 | 町有 | 金泉山「長楽寺記」 | 清水 | 平成12年3月31日 |
| 50 | 町有 | 大安山禅定寺 唐櫃 | 広見 | 平成7年2月27日 |
| 51 | 町民 | 鬼北文楽 | 岩谷 | 平成9年7月25日 |
| 52 | 町民 | 五つ鹿踊り 上鍵山 | 上鍵山 | 昭和55年11月5日 |
| 53 | 町民 | 花とび踊り 節安 | 父野川上 | 昭和55年11月5日 |
| 54 | 町民 | 等妙寺法衣一式(香色法衣・黄緞七条袈裟及び座具) | 芝 | 平成25年3月26日 |
| 55 | 町記 | 多武が森城跡 | 広見 | 昭和52年10月28日 |
| 56 | 町記 | 武士狩野古戦場 | 近永 | 昭和52年10月28日 |
| 57 | 町記 | 鳥屋の森城跡 | 生田 | 昭和52年10月28日 |
| 58 | 町記 | 一の森城跡 | 吉波・西仲 | 平成7年2月27日 |
| 59 | 町記 | 勝山城跡 | 上大野 | 昭和55年11月5日 |
| 60 | 町記 | 龍天廃寺跡 | 下大野 | 平成7年2月27日 |
| 61 | 町記 | 下大野庄屋跡 長屋門 | 下大野 | 平成7年2月27日 |
| 62 | 町記 | 興野々寺山遺跡 | 興野々 | 平成25年3月26日 |
| 63 | 町記 | 近永代官所跡 | 近永 | 平成25年3月26日 |
| 64 | 町記 | 笛吹池 | 柏田 | 平成7年2月27日 |
| 65 | 町記 | 奈良天満神社社叢 | 奈良 | 平成7年2月27日 |
| 66 | 町記 | 高鴨神社社叢 | 興野々 | 平成30年11月26日 |
| 67 | 町記 | 西野々のクロガネモチ | 西野々 | 昭和52年10月28日 |
| 68 | 町記 | 法師庵の大イチョウ | 大宿 | 昭和52年10月28日 |
| 69 | 町記 | 鳳凰山成杖寺大イチョウ | 内深田 | 平成7年2月27日 |
| 70 | 町記 | 武左衛門大イチョウ | 上大野 | 昭和55年11月5日 |
| 71 | 町有 | アンモナイト化石中のアナシビリテス・オーノイ(貝の化石)外 | 下鍵山 | 昭和55年11月5日 |
| 72 | 町記 | 甌穴群 | 小倉 | 昭和52年10月28日 |
| 73 | 町有 | 水分層 | 奈良 | 平成7年2月27日 |
| 74 |
町民 |
安森鍾乳洞 | 小松 | 平成7年2月27日 |
| 75 | 町有 | 堆朱香合 等妙寺 | 芝 | 令和3年10月2日 |
| 76 | 町有 | 上鍵山日吉神社 棟札 | 上鍵山 | 令和7年3月10日 |
※国有:国指定有形文化財、国民:国指定民俗文化財(無形・有形)、国記:国指定記念物(史跡名勝天然記念物)
国登:国登録有形文化財(建造物)
県有:県指定有形文化財、県民:県指定民俗文化財、県記:県指定記念物
町有:町指定有形文化財、町民:町指定民俗文化財、町記:町指定記念物
国指定重要文化財「善光寺薬師堂附厨子」
| 善光寺薬師堂は、医王山善光寺境内にある仏堂です。屋根は宝形づくり茅葺きの三間堂で、堂内の中央に四天柱を立てた形式は平安時代以来の一間四面堂の伝統を継承した室町期の唐様(禅宗様)の特徴を備えた建物です。四国では最南端に位置する貴重な物件として国の重要文化財に指定され、昭和57年(1982)には解体修理を完了しています。この修理時に内陣天井板受桁に文明15年(1483)の墨書が確認され、おおむねこの頃の建築ということが判明しました。 |  |
|
堂内にある厨子は一間厨子で入母屋造り板葺、禅宗様の建造物です。薬師堂と同じ頃の制作とみられ、保存状態がよく、薬師堂とともに国指定重要文化財に指定されています。 厨子内に安置される本尊は、木造薬師如来坐像(町指定有形文化財)で、像内背部墨書銘より薬師堂の創建より1世紀ほど古い、正平15年(1358)に大仏師肥後法眼覚朝とその弟子によって造立されたことがわかります。善光寺の歴史や地域の歴史を語るうえで欠かせず、また、銘記を有した南北朝期の作品としても大変貴重なものといえます。 |
 |
県指定史跡「岩谷遺跡」
|
岩谷遺跡は、広見川東岸の河岸段丘上にある縄文後期(約4000年~3000年前)の遺跡です。この遺跡は、上・下二段に分かれており、どちらからも多量の縄文後期の土器や石器が発見されています。特に下段では、幅75メートルの範囲にわたって円形配石遺構(環状列石)や石組遺構が多数確認されました。石器には、石皿や叩き石、漁網に使ったとみられる石錘、石鏃、スクレーパーなど、狩猟採集に伴うもののほかに、打製石斧が多数伴っていました。近年の研究では、土堀具や鍬として使用され、畑作などの農耕に伴う可能性があるものとされています。 また、発見された出土遺物の中には、祭儀用と見られるペンダント風の石製装飾品も含まれており、豊穣・豊漁を祈念した祭祀遺構ではないかと考えられています。 |
 |
国指定史跡「等妙寺旧境内」
|
鬼北町大字芝に所在する奈良山等妙寺(天台宗)は、元応2年(1320)、理玉和尚(りぎょくかしょう)の開山と伝えられます。理玉は淡路出身で、天台宗総本山の比叡山で仏道を学びました。理玉和尚は、中央の文献で、静義上人、ぎ求上人という名前であったことがわかっています。 平安後期から鎌倉時代にかけて比叡山では、僧兵を構えるなど、仏道修行を蔑ろにし、僧として遵守すべき仏の教えである戒律が守られない破戒の状態が一般化していました。こうした風潮のなかから、比叡山西塔の別所黒谷を拠点とする僧らを中心に、僧たる原点を見つめなおし、天台宗祖最澄が伝えた教えを復興しようという戒律復興の運動が興りました。彼らは自ら「天台律」を名乗り、「戎家」と称して、最澄の伝えた十二年籠山行を実践し、貴賤を問わず広く戒律を伝えるなど布教や庶民救済活動を展開することで、戒律の復興に努めました。 この法門は興円のときに思想大系がまとめられ、後醍醐天皇の篤い帰依を得た弟子の恵鎮円観のとき、京都東山の法勝寺の修造を通じて戒律道場とし、布教活動の拠点としました。さらに弟子らを各地に派遣し、寺院を創設して全国へと布教活動を展開しました。その弟子の一人が理玉であり、創設された寺院が等妙寺です。比叡山に匹敵する修行地を求めてこの地を選び、創られたものといえます。 等妙寺の主な歴史は、「等妙寺縁起」や「宇和旧記」、末寺であった歯長寺(西予市宇和)に伝わる「歯長寺縁起」などからうかがい知ることができます。当時の宇和郡は、「宇和庄」という伊予国最大の庄園で、西園寺氏が領していました。寺院の造営には、西園寺家被官で庶務代官であった開田善覚や西園寺家の庇護があったといいます。元徳2年(1330)には十二坊まで造営し、密教道場としての威容が整い、以後、理玉から旭栄まで25世260年にわたって寺運はますます栄えたといいます。ところが、豊臣秀吉の四国征伐の後、天正15年(1587)戸田勝隆の宇和郡入りの際、寺領や寺宝をすべて没収され、加えて翌天正16年(1588)に火災により、伽藍も焼失。隆盛を極めたさしもの名刹も一度に荒廃したといいます。しかし、火災から2年後、麓の霊光庵跡地にて再興され、江戸時代には宇和島藩伊達氏の庇護を得て存続し、今の等妙寺へとつながっています。 等妙寺旧境内は、町の南西に位置する鬼ヶ城連山のうち、郭公岳(標高1,010m)の中腹から麓にかけての範囲に寺院の中心となる伽藍が築かれています。天正の火災以後は、藩の御立山(御用木林)として管理され、明治期には国有林、昭和には町有林となりました。聖地として認識されていたため開発等が入ることなく、広大な伽藍が中世の姿そのままで遺されています。特に各所で駆使し築かれた石積みは注目され、当時の土木技術水準の高さをうかがい知ることができます。また、寺院の中枢である本堂跡や本坊跡が確認された平坦部A(如意顕院跡)の調査から、石積みを駆使した平場造成が14世紀前半の開山期にさかのぼること、15世紀前半から後半にかけて大規模な改変がなされていること、また、庭園地区では、苑池が確認され、その直上に位置する平坦部A-2(観音堂跡)とともに、その形成が開山期以前、つまり等妙寺の前史にあたる寺の発祥地であることがわかってきました。 等妙寺がなぜこの地に造られたのか。それは背後の広大な山岳霊場「奈良山」に対する信仰が原点にあります。等妙寺本尊である如意輪観音像は鎌倉前期の作で、鎌倉時代には観音霊場として開かれ、のちに理玉らが修行地を求めて天台の戒律復興・修行の拠点として等妙寺を創設したという歴史の脈絡が見えてきています。
|
|
、