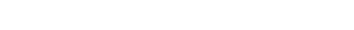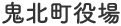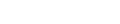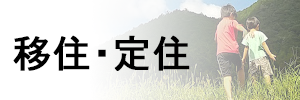本文
文化財~善光寺(木造薬師如来坐像および二天十二神将)~
医王山善光寺
 木造薬師如来坐像
木造薬師如来坐像
医王山善光寺は曹洞宗の寺で、国の重要文化財に指定されている薬師堂と厨子、そのなかには町指定有形文化財の木造薬師如来坐像が安置されています。その奥には、江戸時代の作である二天・十二神将が置かれています。
木造薬師如来坐像一体は、像高70cm、雲光背85cm、台座76cmの結跏趺坐(諸仏の坐像にはこの姿勢が多い)で左手に薬壷を捧げ右手に施無畏印(如来像にはこの印相が多い)を結ぶ型通りの薬師如来像です。木材は桧材で、寄木造り、鎌倉期の作。ただし、薬壷は欠落しています。光背と台座は後補のようです。

 二天・十二神将
二天・十二神将
木造二天立像2体は、像高50cmで桧材、寄木造りで、多聞天(毘沙門天)と増長天であることがわかります。十二神将12体は、像高30cmの桧材、寄木造り、多少の欠損はありますが12体ともそろっています。
十二神将というのは、東西南北の四方をまもるという意味に、さらに中国の方位の考え方が加わって、四方を12に割って、そこにそれぞれ守護神がいる、それが十二神将です。
ところが、この十二神将もまた仏たちが変身したもので、宮毘羅大将は弥勒の変身、因達羅大将は地蔵の変身とされ、それぞれに本地仏があります。十二方というと子丑寅…という方位を思い出しますが、その場合は人間であり、十二神将というときの中心は薬師如来です。薬師の世界は東方にあるといわれており、ここを十二神将が十二方で守っているが、実は各神将は天部でなく、大日如来や阿弥陀如来、文殊菩薩、その他の仏たちが変身して、この十二神将のように憤怒の姿で防衛しているというのです。ですから本尊の薬師如来に願いごとをすると、いろいろな仏がそれぞれに応じて協力してくれるというわけです。(町指定有形文化財)
所在地
小松
指定年月日
昭和52年10月28日