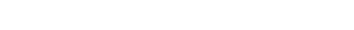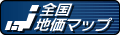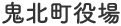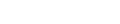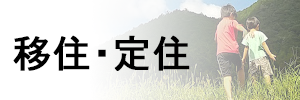本文
固定資産税
固定資産税制度について
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して、「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産税の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税は町税の約半分を占め、行政サービスを提供するための財政を支える基幹税目として重要な役割を果たしています。
固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
|
土 地 |
30万円 |
|---|---|
|
家 屋 |
20万円 |
|
償却資産 |
150万円 |
税額
固定資産税の税率は1.4%です。
課税標準額 × 税率1.4% = 税額 となります。
固定資産税の納付
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者へ税額が通知され、通常年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて納税を行います。納付書による指定金融機関での現金での納付の他、口座振替による納付もできます。
※口座振替での納付を希望される場合は、「町税等の口座振替制度について」をご覧ください。
固定資産税の課税のしくみ
土地に対する課税
1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
2 地目及び地積
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目により評価します。地積は、原則登記簿上の地積によります。
3 評価額及び課税標準額の算出方法
(1)山林・田・畑
標準となる土地(標準地)を選定して、それに比準して算出した評価額を課税標準額とします。
(2)原野・雑種地
現況により、近隣の宅地や農地等に比準して評価額を算出し、調整措置を適用して課税標準額を算出します。
(3)宅地
鬼北町では、2つの評価方法を併用して評価しています。
ア 市街地宅地評価法(路線価方式)
標準宅地の鑑定評価額を基に各道路に付けられた1平方メートル当たりの価格(路線価)から評価額を算定する方法であり、具体的には、道路ごとに幅員、歩道・舗装の有無、公共施設や商業施設等への距離等を考慮し価格を算定します。
道路に接する宅地の評価額は、この路線価格を基礎とし、画地計測補正(奥行、間口、形状、角地など)をして算出します。この評価方法は、比較的厳密な計算を行うことが必要であると認められる地域、すなわち市街地的な形態を形成する地域については、できるだけこの方法によることが望ましいとされています。
イ その他の宅地評価法
町内の宅地の道路状況、公共施設の状況、家屋の疎密度等により利用状況がおおむね類似している地区(状況類似地区)を区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地(標準宅地)の評点数に基づいて、所定の「宅地の比準表」を適用し、各筆の評点数を求める方法です。
4 路線価・標準宅地の公開について
宅地の標準的な価格の閲覧制度として、路線価及び標準宅地を記載した図面と単位地積あたりの価格を窓口で公開しています。また、インターネットでも「全国地価マップ<外部リンク>」(財団法人資産評価システム研究センター作成)にて、鬼北町内の路線価等を公開しています。
5 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます(上限:家屋の床面積の10倍まで)。なお、長期間居住者がいない場合、併用住宅用地、また1筆の宅地について土地の利用状況が異なる場合は、取り扱いが異なります。
(1) 小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。
(2) 一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。
6 土地に関する申請
(1) 課税地目を変更したい場合
土地の利用状況の変更のため、課税地目を変更したい場合は「固定資産(土地)修正申出書」を提出してください。
提出後に当方で申出が正当であるか現地調査をさせていただきます。12月末までに申請があり、申出が正当であるものについて次年度から課税地目を変更いたします。
(2) 宅地の住宅用地特例適用や変更を申請したい場合
新築や改築により住宅用地となった場合、住宅の取り壊しにより住宅用地では無くなった場合等、住宅用地の特例適用や変更が必要な場合は、「固定資産税宅地の住宅用地(適用・変更)申告書」を提出してください。書類審査及び現地調査をさせていただき、申請が正当であるものについて、次年度から住宅用地の特例を適用(変更)いたします。
なお、前年から変更が無い場合は、新たに提出する必要はありません。
必要書類
 固定資産税宅地の住宅用地(適用・変更)申告書 [PDFファイル/195KB]
固定資産税宅地の住宅用地(適用・変更)申告書 [PDFファイル/195KB]
※申告者が申請地に住所を有しないが、住宅用地の特例を申請する場合
〇借家として第三者に貸している場合
賃貸契約書の写し
〇その他の場合
毎月1回以上居住していることが確認できる書類 (電気、ガス、水道料金の明細または領収証1年分)
家屋に対する課税
1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
(1) 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
〇再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
〇経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
(2) 新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれます。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
※再建築価格 = 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
2 新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
(1) 適用対象
ア)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
イ)床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(2) 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象になりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(3) 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
(4) 減額される期間
ア 一般住宅
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
イ 長期優良住宅
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※町への申告書の提出が必要です。
3 家屋に関する申請
(1) 未登記家屋の所有者変更
登記されていない家屋については町で所有者の変更ができます。所有者変更を希望される方は下記の書類を提出してください。
なお、この申請は、固定資産税を課税するために必要な事項を届け出るためのもので、不動産登記法の登記とは関係ありません。第三者に対して所有権を主張するのであれば、法務局への登記が必要となります。
必要書類
〇相続の場合
・遺産分割協議書の写し
※遺産分割協議書のかわりに「相続に係る承諾書」でも可能ですが、相続に係る戸籍謄本の写しが必要です。
・相続関係説明図(戸籍謄本の写しを添付する場合は不要)
・相続人全員の印鑑証明の写し
〇売買の場合
・売買契約書の写し
・旧所有者及び新所有者の印鑑証明の写し
〇贈与の場合
・贈与契約書等の写し
・旧所有者及び新所有者の印鑑証明の写し
※新所有者が町外の方の場合は、新所有者の住民票も必要となります。
(2) 固定資産(家屋)修正申出書
家屋を取り壊したり、用途を変更した場合等、家屋について修正が生じた場合は、「固定資産(家屋)修正申出書」を提出してください。
必要書類
〇滅失(取り壊し)の場合
・取り壊し年月日が分かる取り壊し業者等の領収証(写し)
償却資産に対する課税
1 定義
会社や個人で工場や商店などを経営している場合、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。なお耐用年数が1年未満の資産、取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)、取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)、自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、課税の対象ではありません。
2 算出方法
(1) 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
(2) 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※この価格が取得価格の100分の5よりも小さい場合は、取得価格の100分の5を価格とします。
固定資産税関係の各種手続きについて
公簿の閲覧や固定資産税の証明等を取るには
公簿の閲覧、証明または複写を希望される方は、申請書に必要事項を記入し請求してください。
なお、窓口へ来られた方が本人または同一世帯の家族以外の方の場合は、原則委任状または同意書が必要となります。申請書に代理人を指定する欄がありますので、下記申請書を事前に印刷しご準備ください。
また、申請者(窓口に来られた方)の本人確認のため、運転免許証や健康保険証の提示をお願いしています。詳しくは「税務証明請求時における本人確認」をご覧ください
※郵送での請求もできますので、希望される方は、「郵送で証明等をとるには」をご覧ください。
|
項目 |
手数料 |
委任状または同意書(※) |
|---|---|---|
| 土地・家屋台帳等の閲覧 |
1件(土地5筆・家屋5棟まで) 200円 |
必要 |
| 土地台帳一覧表の閲覧 (評価額記載無し) |
1件(土地5筆・家屋5棟まで) 200円 |
不要 |
| 評価証明・公課証明など |
1件(土地5筆・家屋5棟まで) 200円 |
必要 |
| 土地・家屋台帳などの記載事項証明 | 1件 200円 |
必要 |
| 固定資産税名寄帳 | 1件(1枚につき) 200円 |
必要 |
| 地籍図・集成図等の複写 | 1件(1枚につき) 200円 |
不要 |
| 住宅用家屋証明 | 1件 1,000円 |
不要 |
※本人または同一世帯の家族以外の方が申請される場合。
閲覧・証明・複写等
 固定資産(閲覧・証明・複写等)申請書 [PDFファイル/158KB]
固定資産(閲覧・証明・複写等)申請書 [PDFファイル/158KB]
納税証明
 諸証明等申請書 (PDFファイル、100キロバイト)
諸証明等申請書 (PDFファイル、100キロバイト)
縦覧帳簿の縦覧
毎年4月1日から4月20日または納期限のいずれか遅い日まで縦覧帳簿の縦覧を行います。縦覧は土地または家屋に対して課する固定資産税の納税義務者の方の求めに応じて縦覧できます。
固定資産の価格に係る不服審査について
固定資産の価格について不服がある場合は、1期分の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査の申し出をすることができます(受付:総務財政課行政係)。
なお、価格以外について不服がある場合は、行政不服審査法による異議申し立てを行っていただくことになります。この場合は納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内が期限となります。
土地・家屋の現況が変更になった場合や家屋を新築・増築した場合
土地の現況地目が変更になった場合や家屋の新築・増築・取り壊し・用途変更等を行なった場合は、お早めに町民生活課までご連絡ください。
また、町外の方で転居し、住所が変更になった場合も、ご連絡をお願いいたします。
よくある質問
(1)私は、昨年の12月1日に自己所有の土地と家屋を売買し、今年の2月15日に所有権移転登記を行ないました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。
今年度の固定資産税はあなたに(売主)に課税されます。
固定資産税における納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿に登記された方(未登記家屋等の場合は家屋補充課税台帳に登録された方)になります。
今回の場合、売買は昨年の12月でありますが、所有権移転登記が今年の2月であるため、1月1日現在は売主であるあなたが所有者として登記されているので、今年度の固定資産税はあなたに課税されます。
(2)父の所有する宅地に住宅を建てて住んでおり、その分の税金を父に払わないといけません。宅地の評価額は4,500,000円で、課税標準額は800,000円と言っていました。税金がいくらになるのか教えてください。
当町の固定資産税の税率は1.4%です。宅地の場合、特例措置等で評価額と課税標準額に差があり、税額を計算する際は課税標準額を用います。この宅地の税金は、課税標準額800,000円に税率1.4%をかければ求められ、11,200円となります。
(3)町内に父から受け継いだ宅地3筆、山林2筆、家屋2棟を所有していますが、家屋の税金がかかっていないようです。町外に住んでいるため、現存するのか分かりません。確かめてもらえないでしょうか。
あなたが所有される家屋の課税標準額は、居宅が120,000円、納屋60,000円、合計で180,000円です。家屋の固定資産税は、その納税義務者が町内に所有する家屋すべての課税標準額を足して、免税点の200,000円未満の場合、課税されません。
これと同様に、土地が300,000円未満、償却資産は1,500,000円未満の場合、課税されません。
なお、家屋が現存するか現存しないかは、本人もしくはこちらに住んでおられる親戚の方等で確認してください。もし、家屋が現存しなかった場合は、申出をしてください。
(4)固定資産の評価替えとは何ですか?
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。したがって、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行なうのが理想的ですが、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要があること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。
なお、今回評価替えは平成30年度に行なわれましたので、次は令和2年度となります。
(5)地価が下がっているのに、どうして土地の税額が上がるのですか。
土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に改める負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて改めている過程にあるものです。
なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、据置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落を評価額に反映しています。
(6)昨年の8月に住宅を取り壊しました。税金がその分安くなると思っていたのですが、反対に高くなりました。どうしてですか。
土地の上に居住している住宅があると、住宅1戸当たり、200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)については課税標準額を評価額の6分の1に、200平方メートルを超える住宅用地(一般住宅用地)部分については3分の1にするという税負担を軽減する特例措置が講じられています。
しかし、住宅を取り壊したことでこの特例措置の適用がなくなり、住宅のあった土地の課税標準額が上がったため税金が高くなったのです。
(7)宅地の一部を耕して野菜を作っています。一部は宅地でなく畑です。畑の部分を畑として課税できないのですか。
建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。一般に農地(田および畑)とは、「耕作の用に供される土地」をいいます。具体的には、「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地をいいます。
(8)今年の1月20日に家屋を取り壊したのですが、その税金がかかりました。どうしてですか。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象として、その年の4月から始まる年度に課税されます。
したがって、この家屋は1月1日には現存していますので、課税の対象となります。
(9)昨年5月に父の固定資産(土地・家屋)をすべて相続し、登記を済ませたはずなのに、父の名前で家屋の固定資産税がきました。どうしてですか。
その家屋は未登記家屋です。本来は登記することが望ましいのですが、未登記家屋については役場町民生活課でも所有者を変更できます。所有者を変更される場合は、「未登記家屋所有者変更申請書 [PDFファイル/197KB]」を提出してください。提出された翌年から所有者が変更されます。
(10) 私道(公衆用道路)にも、固定資産税は課税されますか。
公衆用道路であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。ただし、私道であっても、所有者が何らかの制限を設けず、多数人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が免除されます。
公共の用に供する道路に対する非課税について [PDFファイル/97KB]
(11)宅地の一部を道路として使っています。課税されるのでしょうか。
公共の用に供する道路は、非課税となります。
本来、私道の非課税適用は分筆された土地が原則ですが、分筆されていない指導についても、道路として広く利用されているなど、一定の要件を満たしていれば該当します。
必要書類(公衆用道路部分の面積が分かる資料)を提出していただき、公衆用道路として確認ができるものに限って非課税とします。
公共の用に供する道路に対する非課税について [PDFファイル/97KB]
(12)平成23年9月に木造の住宅を新築したのですが、平成27年から固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。
一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課されるようになった年度から、
〇一般住宅 ・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)
〇長期優良住宅・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)
に限り、一定の部分の税額が2分の1に減額されます。
この住宅(一般住宅)の新築軽減期間は、平成24年度から平成26年度の3年間となり、平成27年度からは新築軽減の適用がなくなり本来の税額に戻ったため、固定資産税が高くなったのです。
(13)木造瓦葺平家建、160平方メートル、評価額(課税標準額)14,000,000円の住宅を新築しました。新築軽減後の税額を教えてください。
この住宅の本来の固定資産税額は、196,000円です。しかし、120平方メートル分までは新築軽減の適用を受けるため、73,500円安くなり、122,500円となります。
(計算方法)
〇本来の税額 14,000,000円×1.4%=196,000円
〇軽減税額 14,000,000円×1.4%×120/160×2分の1=73,500円
〇軽減後の税額 196,000円-73,500円=122,500円
(14)昭和40年に新築した木造住宅に住んでいます。最近は修繕の回数も多くなり、価値は年々下がっているはずなのですが、どうして評価額が下がらないのですか。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に、家屋の建築後の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、以前から据え置かれている価格を下回るまでいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
(15)昭和25年に祖父が建てた住宅があり、誰も住んでいないのに、税金がかかっています。住んでいないのに税金を払わなければならないのでしょうか。
家屋とは、
(1) 外気と分断され、(2) 土地に定着し、(3) 造られた用途で継続的な利用ができるもの
をいい、これらの条件を満たす限り、固定資産税が課されます。
しかし、家屋としての条件を満たさなくなった場合、例えば、屋根が台風で飛ばされ、それ以後修繕する予定がない場合等、「外気との分断性」がなくなり、家屋として認定できないため、固定資産税は課されません。
家屋への課税は、住んでいる住んでいないにかかわらず、家屋として認定される限り、課税されます。
(16)住宅に付属して建てた車庫や畑の近くに建てた倉庫等の簡易な建物についても、固定資産税はかかりますか。
簡易な構造の建物であっても、
「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」
であれば、課税の対象になります。
(17)来年、柚子商品を製造する工場を建てようと考えています。土地と家屋以外にこの工場内の事業用のパソコンや機械などに税金がかかると聞いたのですが、本当ですか。
固定資産税は、土地と家屋以外に会社や個人で所有する事業用の資産(償却資産)にも課されます。その内容は、構築物(塀、舗装、煙突等)、機械及び装置(ポンプ、動力配線設備等)、工具・器具・備品(自動販売機、作業工具、応接セット、ロッカー等)等です。
毎年1月1日現在に償却資産をお持ちの方は、その年の1月31日までにその資産状況を申告していただく必要があります。
(18)私は高齢のため、新たな働き口もなく、年金の収入だけで暮らしています。年金も少なく、生活が苦しいので、固定資産税を免除してもらえないでしょうか。
火災や災害等により固定資産に損害を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等に限り、申請により固定資産税の減免措置が可能です。
固定資産税は、資産の所有・価値に応じて負担いただくものなので、収入や年齢の違い等による税の軽減はできません。
(19)仕事が忙しく、金融機関へ行って固定資産税を納付する時間がなかったり、忘れたりすることがよくあります。便利な口座振込で納税したいのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
町税等を納付する方法に口座振替制度があります。この制度は、金融機関にわざわざ行かなくても納期限の日に自動的に預金から納付できる便利で確実な制度です。
納税を忘れて、納期限を越えると督促手数料や延滞金を納付しなければならない場合がありますので、その点からも便利な口座振替制度をご利用ください。
手続きの方法は、「町税等の口座振替制度について」を参照ください。