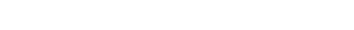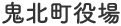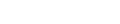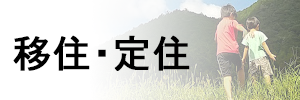本文
国民健康保険税
税金
国民健康保険税
国民健康保険について
国民健康保険は、加入者(以下、「被保険者」)の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療機関で治療を受けることができるように、日頃からお金を出し合う相互扶助の制度です。
日本では、国民皆保険のもとすべての人がいずれかの公的医療保険に加入することとなっています。したがって、職場の社会保険等(健康保険、船員保険、共済組合等)に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険へ加入しなければなりません。
この国民健康保険の財源となるのが、国や県からの負担金、被保険者の皆さんが納めていただく国民健康保険税となります。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者となります。そのため、世帯主本人が職場の社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となり、世帯主宛てに納税通知書等が送付されます。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税の内訳は、国民健康保険の被保険者が診療を受けた時の医療費の支払い等に充てる「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支える「後期高齢者支援金分」、介護保険の財源となる「介護納付金分」の3つから構成されています。このうち、医療給付費分と後期高齢者支援金分については0歳から74歳までの被保険者が、介護納付金分については40歳から64歳までの被保険者がそれぞれ対象となります。
国民健康保険税の計算については、被保険者の前年中の所得や当年度の固定資産税、世帯内の被保険者の人数等に応じて決定されることとなり、次の税率を乗じて合算した金額が1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険税額となります。
令和7年度の税率
|
1 医療給付費分 (0歳から74歳) |
2 後期高齢者支援金分 (0歳から74歳) |
3 介護納付金分 (40歳から64歳) |
|
|---|---|---|---|
|
A 所得割 |
所得割課税標準額× 7.2% |
所得割課税標準額× 2.5% |
所得割課税標準額× 2.2% |
|
B 資産割 |
固定資産税額× 12.5% |
固定資産税額× 5.0% |
固定資産税額× 4.0% |
|
C 均等割 |
被保険者1人につき 17,100円 未就学児1人につき 8,550円 |
被保険者1人につき 7,000円 未就学児1人につき 3,500円 |
被保険者1人につき 7,400円 |
|
D 平等割 |
1世帯につき 19,000円 |
1世帯につき 5,400円 |
1世帯につき 4,100円 |
|
賦課限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
|
年間保険税額 (1)医療給付費分(A+B+C+D)+(2)後期高齢者支援金分(A+B+C+D)+ |
|||
注1 所得割課税標準額 前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額となります。
注2 賦課限度額 A~Dを合算した金額が賦課限度額を超えた場合は、限度額が保険税額となります。
総所得金額等 について
(1)具体例は、次のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額 ※退職所得は含まれません。
(2)国民健康保険税における所得割額の算定には、次の控除が認められています。
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
(3)国民健康保険税における所得割額の算定には、次の控除は認められません。
雑損控除(繰越控除含む。)、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除
年度途中の加入、脱退
年度途中で被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、社会保険等脱退・加入)が生じた場合は、加入期間に応じて税額を月割で計算し、届出月の翌月に税額変更通知書等を送付いたします。
◆年度途中で加入 - 加入した月から月割で計算します
- ◆年度途中で脱退 - 脱退した月の前月までの分を月割で計算します
国民健康保険を脱退した後の保険税の納付(精算)について
国民健康保険税の1期当たりの納付金額は、4月から翌年3月までの1年間(途中加入の場合は、加入月から翌年3月まで)の保険税額を、年間納付回数である9回(途中加入の場合は、残りの納付回数)で割ったものとなっており、1ヶ月分の保険税額とは必ずしも一致しません。転出や社会保険等に加入されるなど国民健康保険を脱退されると、脱退した月の前月分までで保険税額は再計算されることとなりますが、脱退時点での納付額が再計算された保険税額よりも少ない場合は、脱退月以降についても納付していただくこととなります。また、脱退時点での納付額が再計算された保険税額よりも多い場合は、納め過ぎとなった分を還付します。
国民健康保険税の軽減措置
低所得世帯に対する軽減
国民健康保険税の納税義務者(世帯主、擬制世帯主)と世帯に属する被保険者の軽減判定所得が、次の基準額以下の場合には、均等割と平等割が軽減されます。
【軽減対象基準額】
|
軽減額 |
|
|---|---|
|
世帯主及び世帯に属する被保険者の前年中の軽減判定所得の合算額が、 43万円 +{10万円 ×(給与所得者等<注2>の数-1) }以下の場合 |
均等割、 平等割が 7割減額 |
|
世帯主及び世帯に属する被保険者の前年中の軽減判定所得の合算額が、 43万円 +(30万5千円×被保険者数<注3>) +{10万円 ×(給与所得者等<注2>の数-1)}以下の場合 |
均等割、 平等割が 5割減額 |
|
世帯主及び世帯に属する被保険者の前年中の軽減判定所得の合算額が、 43万円+(56万円×被保険者数<注3>) +{10万円 ×(給与所得者等<注2>の数-1)}以下の場合 |
均等割、 平等割が 2割軽減 |
注1 賦課期日(4月1日)時点の世帯(擬制世帯主含む。)の軽減判定所得で判定しますので、その後の加入人数の異動(出生、死亡、転入、転出等)では再判定をしません。ただし、年度途中での新規加入世帯や世帯主の変更があった場合はその時点で判定します。
注2 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金所得者(65歳未満の場合60万円超、65歳以上の場合125万円超)である方をいいます。
注3 被保険者数には同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。
注4 前年中の所得(収入)がない方または少ない方、障害年金や遺族年金の非課税収入のみの方についても、所得申告が必要です。世帯の中に申告をしていない方がいる場合は、上記軽減措置が受けられませんので必ず申告してください。
軽減判定所得について
軽減判定に用いる所得は、次の点で総所得金額等と異なります。
(1) 65歳以上の公的年金受給者については、年金所得から15万円を控除した額となります。
(2) 分離譲渡所得については、特別控除前の額となります。
(3) 事業所得については、専従者控除前の額となります。
非自発的失業者に係る軽減措置
会社の倒産や、解雇等により離職された方のうち、次の要件をすべて満たす方は、申請により所得割が軽減されます。
対象者
(1)平成21年3月31日以降に離職(退職)された方。
(2)離職日の翌日(国民健康保険加入日)時点で、年齢が65歳未満の方。
(3)公共職業安定所(ハローワーク)から交付を受けた「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかのコード番号が記載されている方。
軽減内容
保険税の所得割を算定する際に、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。なお、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、雑所得等)については軽減の対象に含まれません。また、同じ世帯に属する被保険者の所得についても軽減の対象となりません。
軽減期間
失業した日の翌日からその翌年度末までの保険税が軽減されます。なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職された場合においても引き続き軽減の対象となりますが、会社の社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退した時点で軽減措置が終了します。
申請方法
印鑑、雇用保険受給資格者証をお持ちの上、町民生活課保険年金係で申請してください。
 (令和)非自発的失業者に係る軽減申請申告書 [PDFファイル/92KB]
(令和)非自発的失業者に係る軽減申請申告書 [PDFファイル/92KB]
後期高齢者医療制度に係る緩和措置
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(以下、「特定同一世帯所属者」)がいる場合は、国民健康保険税の大幅な上昇を避けるため、次の緩和措置が受けられます。
低所得世帯に対する軽減
均等割と平等割の軽減判定をする際に、特定同一世帯所属者も含めて判定します。
平等割の軽減
特定同一世帯所属者と同じ世帯の国民健康保険の被保険者が1人の世帯(以下、「特定世帯」)は、最初の5年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が2分の1軽減となります。
5年経過後の世帯(以下、「特定継続世帯」)については、引き続き3年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が4分の1軽減となります。なお、この軽減措置は世帯主の変更や加入人数の変更があった時点で終了します。
被用者保険の旧被扶養者に係る減免
職場の社会保険等(国民健康保険組合除く。)に加入されていた方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行された場合、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方(以下、「旧被扶養者」)について、次の要件をすべて満たす方は、申請により、当分の間の保険税が減免されます。
対象者
(1)国民健康保険加入日時点で、年齢が65歳以上の方。
(2)国民健康保険加入日の前日に社会保険等の被扶養者であった方。
(3)国民健康保険加入日の前日に扶養関係にあった社会保険等の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった方。
減免内容
|
所得割 |
全額を免除 |
|---|---|
|
資産割 |
全額を免除 |
|
均等割 |
2分の1を減免 |
|
平等割 |
2分の1を減免(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。) |
注1 均等割と平等割の減免については、7割軽減、5割軽減の対象世帯を除きます。
注2 2割軽減世帯については、均等割と平等割を10分の3減免します。
注3 特定継続世帯の平等割については、4分の1減免します。
注4 2割軽減対象の特定継続世帯の平等割については、10分の1減免します。
申請方法
印鑑をお持ちの上、町民生活課保険年金係で申請してください。
国民健康保険税の納付方法
普通徴収
7月に年間の保険税額が決定し、7月中旬に納税通知書及び納付書を発送いたしますので、4月から翌年3月までの1年間分を、7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます。なお、年度途中で国民健康保険に加入した場合は、残りの納付回数で納付していただくこととなります。
納付書による納付
納付書は、7月以降翌年3月まで毎月中旬に発送いたしますので、次のいずれかの方法により納付してください。
(1)指定金融機関(えひめ南農業協同組合)または指定代理金融機関(愛媛銀行、伊予銀行)、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口またはコンビニにおいて、納付書と現金をお持ちの上納付する方法
(2)スマートフォン決済アプリで納付する方法
口座振替による納付
ご指定の口座から、各納期限の日に自動で保険税が振替されます。口座振替をご利用される場合は、事前に金融機関での申し込みが必要です。
詳しくは、「口座振替・税証明・納期」をご覧ください。
特別徴収
平成20年4月から、公的年金受給者を対象として特別徴収(年金天引き)が開始されました。
対象者
世帯主が国民健康保険に加入しており、次の要件をすべて満たす場合は、国民健康保険税が世帯主の年金から天引きされます。
(1)世帯の国民健康保険被保険者すべてが65歳以上74歳以下である。
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している方。
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えていない方。
徴収方法
年金給付月(偶数月)に年金から保険税が天引きされます。
|
令和7年度 |
|||||
|
仮徴収 |
本徴収 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
前年所得が確定するまでは、仮算定(前年度税額基準)された保険税額を徴収します。 〔新規の方〕 〔継続の方〕 |
7月に令和7年度保険税額が決定しますので、本算定された保険税額を徴収します。 〔新規の方〕 〔継続の方〕 |
||||
あなたの世帯の納付方法を判定します
このフローチャート図は世帯主の方を対象としておりますので、世帯主の方がお試しください。
年齢については令和7年4月1日を基準にお考えください。
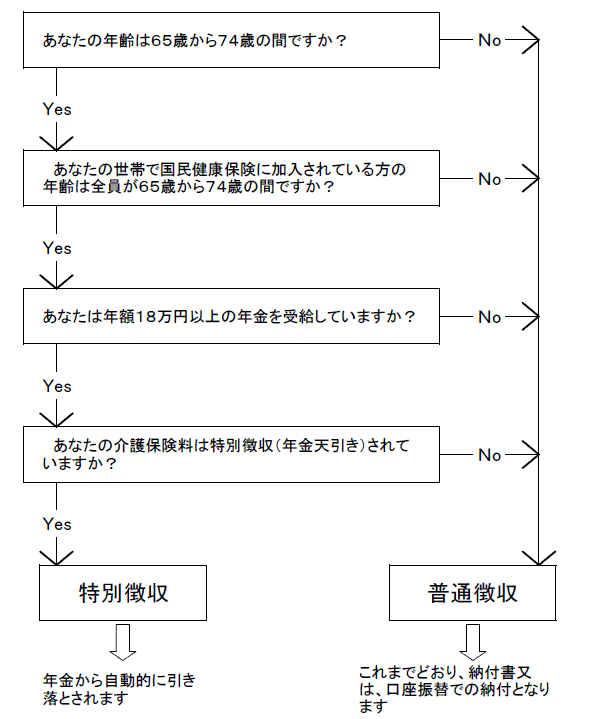
納付方法の変更
上記の公的年金受給者については、原則特別徴収による納付となりますが、次の要件を満たす方は申し出により納付方法を変更することができます。変更を希望される方は、印鑑をお持ちの上、町民生活課課税管理係へお越しください。
(1)申出時点において滞納がないこと。
(2)今後の納付方法を口座振替とすること。
注1 納付方法変更後、口座振替不能により未納となった場合は、本人の意思に関わらず特別徴収へ変更します。
注2 申出から納付方法が変更されるまでに最短で2ヶ月かかります。
 (令和)国民健康保険税納付方法変更申出書.pdf [PDFファイル/96KB]
(令和)国民健康保険税納付方法変更申出書.pdf [PDFファイル/96KB]
お問い合わせ先
-
国民健康保険税については
- 鬼北町役場 町民生活課 課税管理係
- 電話 0895-45-1111(内線 2121・2122・2123)
【参考リンク】 国民健康保険税Q&A
-
国民健康保険事業については
- 鬼北町役場 町民生活課 保険年金係
- 電話 0895-45-1111(内線 2114・2115・2116)