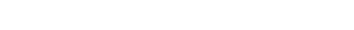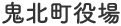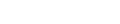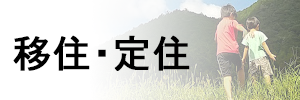本文
後期高齢者医療制度
保険年金
後期高齢者医療制度
はじめに
75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方)は、「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」の被保険者となって医療を受けます。この制度は、高齢者の皆さんが安心して医療を受けることが出来るよう、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となり運営する制度です。
制度のしくみ
-
対象となる方
◆75歳以上の人【※誕生日当日から後期高齢者医療制度に加入することになります。】
-
◆65歳以上で一定の障害のある人(届出が必要です。)【※届出により加入をした一定障害のある65歳以上75歳未満の人は、届出により取り止めることができます。】
-
制度の運営
-
この制度の運営は、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営します。
【参考リンク】 愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
広域連合の役割 市町の役割 ○被保険者証発行、資格の審査
○保険料の決定
○医療費の給付
など運営全般○保険料の徴収
○申請受付
○被保険者証の引渡し
など窓口全般届出について
以下の場合は、市町窓口での届出が必要です。
届出の際には、届出者本人の「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」、各種手続きに必要な書類等をお持ちの上、お越しください。
こんなとき 届出に必要なもの 65歳以上で一定の障害のある人が後期高齢者医療保険に加入するとき 身体障害者手帳等 75歳未満の人が後期高齢者医療保険を脱退するとき 被保険者証 鬼北町から転出するとき 被保険者証 鬼北町に転入してきたとき 負担区分証明書(県外転入のみ) 住所・氏名が変わったとき 被保険者証 被保険者証を紛失したとき 本人確認ができる書類 生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、生活保護開始決定通知書 生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書 死亡したとき 死亡した人の被保険者証 保険料について
保険料の決まり方
-
被保険者の皆様に等しくご負担いただく均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計で、個人単位で計算されます。また、保険料率は、2年ごとに見直しが行われます。県内は、統一の料率となります。
-
被保険者の保険料=イ 均等割額+ロ 所得割額
【令和6、7年度】
イ 均等割額:51,930円
ロ 所得割額:(所得-43万円)×10.16%
※保険料の限度額(上限)は令和6年度が73万円、令和7年度が80万円です。ただし、令和6年度に新たに75歳に到達する方は、限度額80万円になります。 -
保険料の軽減
所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。
◆均等割額の軽減
-
世帯の総所得金額等
(世帯主と被保険者により判定)軽減割合 【43万円+10万円×(★給与・年金所得者の数-1)】以下の世帯 7割 【43万円+29.5万円×(世帯に属する被保険者数)+10万円×(★給与・年金所得者の数-1)】以下の世帯 5割 【43万円+54.5万円×(世帯に属する被保険者数)+10万円×(★給与・年金所得者の数-1)】以下の世帯 2割 ★一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給〈60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)〉を受ける方 ※ 均等割額の軽減判定をする際、公的年金を受給されている方は、所得から15万円が控除されます。 -
◆被用者保険の被扶養者であった方(平成31年度~)
-
被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
-
保険料の納め方
-
◆特別徴収
-
年金支給月に保険料が天引きされます。4月・6月・8月が仮徴収、7月本算定後、10月・12月・2月が本徴収となり、次の方が特別徴収の対象となります。
年間18万円以上年金を受給されている方、介護保険において特別徴収の対象者の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
※年金天引きの対象となる方でも、口座振替による納付も可能な場合があります。詳しくは町民生活課課税管理係までお問い合わせ下さい。 -
◆普通徴収
-
町が発行する納付書または口座振替により納めます。(7月から3月まで計9回)
-
医療機関を受診するとき
-
一部負担金・所得区分について
-
自己負担割合が3割に該当しても、次のいずれかの要件に該当する場合は、申請により2割または1割負担となります。自己負担割合
所得区分
要件
3割
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる方
2割
一定以上の所得がある方
現役並み所得者(3割)に該当せず、同一世帯員の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上(同一世帯員の被保険者が2人以上の場合は、合計金額が320万円以上)ある方
1割
一般
上記3割、2割に該当しない方
低所得者
・単身世帯の場合、収入額が383万円未満であるとき
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満であるとき
・同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳から74歳の人がいる場合、被保険者と70歳から74歳の人の収入の合計が520万円未満であるとき -
自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に医療機関に支払った負担額が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。(支給対象者には、愛媛県後期高齢者医療広域連合より文書でお知らせをいたします。また、一度申請をすると、次回から高額療養費の支給申請をする必要はありません。)
外来は、個人ごとに計算され、入院については、世帯内にいる被保険者の負担額も合算して計算されます。◆申請に必要なもの・・被保険者証、通帳、マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カード)
※1 「+(医療費-○○円)×1%」は医療費が○○円を超えた場合、超過額の1%を加算。所得区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※1)
【140,100円】(※2)現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※1)
【93,000円】(※2)現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※1)
【44,400円】(※2)一般2 18,000円または
【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用(※3)
(年間上限144,000円)57,600円
【44,400円】(※2)一般1 18,000円
(年間上限144,000円)低所得者2 8,000円 24,600円 低所得者1 15,000円
※2 [○○円]は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
※3 一般2に該当する方の外来受診について、1か月にかかる自己負担増を最大3,000円に抑えるための措置。(令和7年9月までの配慮措置) - ※低所得の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療費の負担限度額や入院時の食事代が減額されます。詳しくは町民生活課保険年金係までお問い合わせください。
-
高額医療・高額介護合算制度
-
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して年間の限度額を超えた額は、申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
高額介護合算療養費の年間の限度額(8月から翌年7月までの1年間)
所得区分 1年間の自己負担限度額 現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 2,120,000円 2 課税所得380万円以上 1,410,000円 1 課税所得145万円以上 670,000円 一般 560,000円 低所得者2 310,000円 低所得者1 190,000円 ◆後期高齢者医療制度に加入されている方で、医療保険と介護保険の両方の負担がある世帯が対象となります。
◆高額療養費が支給されている場合は、その額を除いて自己負担額を計算します。
-
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院時の食費は、決められた負担額以外は、愛媛県後期高齢者医療広域連合が入院時食事療養費として支給します。
入院時食事代の標準負担額(令和6年6月から)
※1 低所得者の入院にかかる食事療養費標準負担額の減額適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要です。入院される前に町民生活課保険年金係で申請を行ってください。所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者 490円 一般 490円 低所得者2 90日までの入院 ※1 230円 過去12か月で91日以上の入院 ※1 180円 低所得者1 ※1 110円 その他について
被保険者が亡くなった時(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して申請により愛媛県後期高齢者広域連合より葬祭費が支給されます。町民生活課保険年金係で申請手続きをしてください。◆葬祭費の額 20,000円
◆申請に必要なもの・・亡くなった方の被保険者証、葬儀を行った方の通帳、葬祭執行者が確認できる書類(会葬礼状等)後期高齢者医療保険特定疾病療養受領証
厚生労働大臣が定める下記の疾病の方は、申請により「後期高齢者医療保険特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関に提示することにより、特定の治療に対して1か月の自己負担限度額が1万円となります。町民生活課保険年金係で申請手続きをしてください。
◆疾病内容
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症)
◆申請に必要なもの・・被保険者証、医師の意見書、マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類)
-
こんな場合は、後で費用が支給されます
以下の場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請して認められれば、支払った費用の一部について払戻しが受けられます。
-
◆コルセットなどの補装具を作ったとき(医師が必要と認めた場合)
◆はり・きゅう・あんま、マッサ-ジなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
◆療養の給付を受けるため、医師の指示により病院や診療所に移送されたときの費用
◆やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けたとき(海外渡航中の治療を含む) -
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、被保険者証を使って診療を受けることができますが、必ず届出をしてください。ただし、医療費は加害者が全額自己負担するのが原則ですので、一時的に後期高齢者医療保険が医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。必ず町民生活課保険年金係へ届出をお願いします。
届出の際には、「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」をお持ちください。
お問い合わせ
保険料について:町民生活課課税管理係 45-1111【内線2123】
その他について:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2116】