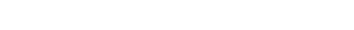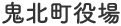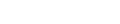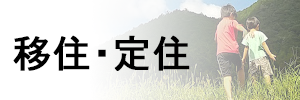本文
国民年金
国民年金について
国民年金の仕組み/国民年金の種別/国民年金の届出
国民年金の保険料/保険料の納付が困難なとき/受けられる年金の種類/老齢基礎年金
障害基礎年金/遺族基礎年金/国民年金の第1号被保険者独自の給付/電子申請
国民年金の仕組み
国民年金は、すべての国民を対象として老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に貢献することを目的としています。
国民年金の種別
日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。(ただし、厚生年金・共済組合の老齢・退職年金を受けられる人を除く。)
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に区分されています。
- 第1号被保険者
- 自営業、農林漁業従事者、学生、自由業などの人
- 第2号被保険者
- 厚生年金、共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合など)の加入者
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年間収入が130万円未満の方)
※また、60歳以上の人でも希望すれば加入することができます。(任意加入)
任意加入できる方
次の条件をすべて満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
国民年金の届出
次のようなときは、町民生活課 保険年金係に届出してください。
第1号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
|
任意加入するとき |
1号 |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) 通帳(※口座引落し用)、金融機関届出印 |
|
| 付加納付を始めるとき | 1号 | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) | |
第2号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 退職したとき | 本人 | 2号→1号 |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) 資格喪失証明書(退職日のわかるもの) |
| 被扶養配偶者 | 3号→1号 |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) 配偶者の資格喪失証明書 |
|
第3号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | 必要なもの | |
|---|---|---|---|
|
配偶者の扶養からはずれたとき |
3号→1号 |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など) 配偶者の扶養からはずれた日のわかるもの |
|
次のようなときは、配偶者の勤務先に届出してください。
第1号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | |
|---|---|---|
| 就職したとき | 被扶養配偶者 | 1号→3号 |
第2号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | |
|---|---|---|
| 退職して、配偶者の扶養になるとき (配偶者が第2号被保険者の場合) |
2号→3号 | |
第3号被保険者の場合
| こんなとき | 種別 | |
|---|---|---|
| 配偶者の加入している年金制度が変わったとき | 3号→3号 | |
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、第1号被保険者は個人で負担します。第2号被保険者は給料からの天引き、第3号被保険者は配偶者が加入している年金制度が負担するため個人で納付する必要はありません。
定額保険料(1ヶ月) 17,510円(令和7年度)
付加保険料(1ヶ月) 400円(第1号被保険者で将来、より多くの年金を希望する人)
■便利な口座振替・クレジットカード納付
保険料の納付には、金融機関等で納付書にてお納めいただく以外に、口座振替・クレジットカード払いによる納付方法があります。
口座振替を希望する方は、預金通帳、印鑑(届出印)をご準備いただき、金融機関、年金事務所、町民生活課保険年金係で手続きしてください。クレジットカード納付をご希望の方は、お近くの年金事務所または町民生活課保険年金係に備え付けの「クレジットカード納付(変更)申出書」にて申請いただけます。
■お得な前納制度
保険料をまとめて納めると、割引がありますのでたいへんお得です。
しかも、毎月納める手間が省けるので納め忘れがありません。
前納申し込みには年度ごとに期限が設けてありますので、詳細は年金事務所または町民生活課保険年金係までお問合せください。
保険料の納付が困難なとき
国民年金の第1号被保険者は毎月、保険料を納めなければなりませんが、法律で定められている要件に該当すれば保険料が免除される「法定免除」、所得が低いなどの理由から申請により免除される「申請免除」という制度があります。
法定免除・・・(1)障害基礎年金の受給者 (2)生活保護法による生活扶助を受けている人など
申請免除・・・所得が低いなどの理由で保険料の免除を承認されたとき
■申請免除
免除の種類は以下の4種です。
- 全額免除 保険料を全額免除する制度です。
- 半額免除 保険料を半額免除する制度で、残りの半額を納めます。
- 4分の3免除 保険料の4分の3を免除する制度で、残りの4分の1を納めます。
- 4分の1免除 保険料の4分の1を免除する制度で、残りの4分の3を納めます。
■申請の方法
「申請免除」を希望する場合は申請が必要です。
申請される年度または前年度において失業したことにより免除申請を行うときは、失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写しを添付してください。
■未納と免除の違い
保険料を納めなかった場合と免除を承認された場合とでは違いがあります。
| 未納の場合 | 免除を受けた場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全額免除 | 半額免除 | 4分の3免除 | 4分の1免除 | ||
| 年金を受けるための受給資格期間には | 受給資格期間に入りません | 受給資格期間に入ります | |||
| 受け取る年金額には | 反映されません | 免除期間は全額納めた場合の3分の1の金額が受けられます | 半額納めれば、全額納めた場合の3分の2の金額が受けられます | 4分の1納めれば、全額納めた場合の2分の1の金額が受けられます | 4分の3納めれば、全額納めた場合の6分の5の金額が受けられます |
| 後から保険料を納めることは | 2年を過ぎると納めることができません | 10年前までさかのぼって納めることができます ※承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合は、経過した年度に応じて加算額がつきます。 |
|||
■納付猶予制度
50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定以下の場合、申請し承認されれば、保険料の納付は不要となります。その期間は、受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
(ただし、猶予の承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合は、経過した年度に応じて加算した額になります。)
■学生納付特例
学生(大学、短期大学、大学院、専門学校、専修学校、各種学校、予備校などに通っている人)で前所得が128万円以下(※令和2年度以前は118万円以下)の場合、保険料の納付が猶予されます。
※免除期間とは多少異なり、年金の受給資格期間には入りますが、10年以内に猶予された期間の保険料を納めなかった場合は受け取る年金額には反映されません。
10年以内に納めた場合(追納)は、納付と同じになります。
申請は、在学証明書(原本)または学生証(コピー可)を準備して年金事務所または町民生活課保険年金係で手続きしてください。
受けられる年金の種類
国民年金の給付は、大きく分けて老齢、障害、遺族の3つに分かれます。
老齢基礎年金・・・高齢になったとき(原則として65歳から)
障害基礎年金・・・病気やけがで障害が残ったとき
遺族基礎年金・・・国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
老齢基礎年金
老齢基礎年金は国民年金保険料を納めた期間、保険料全額免除期間、保険料部分免除納付期間、学生納付特例期間などを合算した期間が10年以上ある人が、65歳から受けられます。
■老齢基礎年金を受けるために必要な期間
老齢基礎年金を受けるためには、次の期間の合計が原則として10年以上必要です。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金第3号被保険者の期間
- 国民年金保険料免除納付猶予期間
- 国民年金保険料部分免除納付期間
- 学生納付特例期間
- 厚生年金・共済組合の加入期間
- 国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
■合算対象期間
合算対象期間は「カラ期間」ともいいますが、国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間のことです。なお、この期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、船員保険、共済組合に加入していた期間で、本人が公的年金に何も加入していなかった期間。
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間。
- 学生であって、平成12年4月以後に学生納付特例の承認を受けて追納しなかった期間。
- 昭和36年4月以後に海外に在住していて国民年金に任意加入していなかった期間。
- 昭和36年4月以後に厚生年金の脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間。
- 昭和36年3月以前の厚生年金、船員保険、共済組合の加入期間で通算対象期間になるもの。
など
■老齢基礎年金の年金額
老齢基礎年金の年金額は満額で831,700円(令和7年度)になります。
年金額の計算は次の方法で計算されます。
831,700円 ×{(保険料納付月数)+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×4分の3)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)} ÷ 加入可能年数×12月
※付加保険料を納めていた場合、納付月数×200円の加算になります。
■加入可能年数
| 生年月日 | 加入可能年数 |
|---|---|
| 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 25年(300月) |
| 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 26年(312月) |
| ~ | ~ |
| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年(456月) |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年(468月) |
| 昭和16年4月2日~ | 40年(480月) |
■老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰上げて受けることができます。また、66歳から75歳までの間で繰下げて受けることもできます。
年金額は、請求したときの年齢によって一定の割合で減額(繰上げの場合)、増額(繰下げの場合)され、その増減率は生涯変わりません。
障害基礎年金
障害基礎年金は、原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで障害者になったときに支給される年金です。
障害基礎年金は、次の要件を満たしているとき、請求することができます。
- 初診日(障害の原因となった病気やけがについて診療を受けた日)が国民年金の被保険者であるとき、または国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満であるとき。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)の障害の程度が1級または2級に該当すること。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料全額免除期間などを合算した期間が3分の2以上あること。
など請求後、日本年金機構の審査(約3か月の期間を要する)を経て支給となります。※ただし、審査は必ず通るとは限りません。(障害の状態や日常生活にどのような支障があるかなど、総合的に審査し決定します。)
■障害基礎年金の年金額
|
昭和31年4月2日以後生まれ |
1,039,625円 + 子の加算額※ |
|---|---|
|
昭和31年4月1日以前生まれ |
1,036,625円 + 子の加算額※ |
|
昭和31年4月2日以後生まれ |
831,700円 + 子の加算額※ |
|---|---|
|
昭和31年4月1日以前生まれ |
829,300円 + 子の加算額※ |
| 2人まで | 1人につき 239,300円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 1人につき 79,800円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、その人の子のある妻または子に支給される年金です。
ただし、被保険者が死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料全額免除期間などを合算して3分の2以上あることが必要です。
■遺族基礎年金の年金額
遺族基礎年金の年金額は定額で、子のある配偶者に支給する額は基本額831,700円(令和7年度)に子の加算額を加算した額となります。
子のある配偶者が受け取るとき
|
昭和31年4月2日以後生まれ |
831,700円 + 子の加算額 |
|---|---|
|
昭和31年4月1日以前生まれ |
829,300円 + 子の加算額 |
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
831,700円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
- 3人目以降の子の加算額 各79,800円
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けるはずだった老齢基礎年金(付加年金を除く)の4分の3の年金額が受けられます。
ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めている人が年金を受けないで死亡したとき、その遺族が受けられる一時金です。
ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金とが競合する場合には選択でいずれかを選ぶことができます。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになります。
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
離婚時の年金分割制度のお知らせ
◆離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
◆離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めにお近くの年金事務所にご相談ください。
※詳しくは、年金機構ホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html<外部リンク>
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて、ねんきんネットより次の申請を電子で行うことができます。
1 国民年金の資格取得(種別変更)届
2 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
3 国民年金保険料の学生の不特例制度
4 付加保険料納付(辞退)申出
5 付加保険料納付該当(非該当)届
6 産前産後免除該当届
7 口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出
8 口座振替辞退申出
電子申請の利用方法
電子申請を行うためには、事前にマイナポータルの開設が必要です。
詳しくは、マイナポータル操作マニュアル(外部リンク)<外部リンク>にてご確認ください。
「マイナポータル」から電子申請を行うと、審査結果はマイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
また、電子申請をする際、必要な添付書類は電子データにより提出いただく必要があります。
JPEG形式(拡張子:jpg)またはPDF(拡張子:pdf)形式を添付することができます。
※iPhoneで撮影した画像の一部はheic拡張子で保存される可能性があるため、撮影前に設定を変更するか、撮影後に上記の拡張子に変更してください。
詳しい操作方法については、こちら(日本年金機構HP)<外部リンク>をご覧ください。