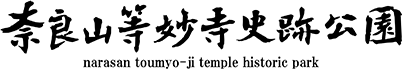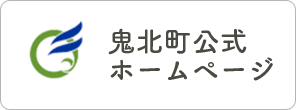本文
等妙寺旧境内と鬼北の鬼伝説
全国で唯一、名前に「鬼」がつく自治体の鬼北町。
鬼北の「鬼」のいわれは、単に「鬼ヶ城山系の北側に位置する地域」というだけではありません。
実は、山の神としての「おに」の信仰が深く関係しています。
等妙寺旧境内と鬼北の「鬼(おに)」
江戸時代初期に成立した「等妙寺縁起」によれば、等妙寺の由来は「曽我物語」(注)の主人公である「曽我兄弟」とその従者「鬼王 段三郎」にまつわる伝承で彩られています。
これを読み解くと、等妙寺は「背後にそびえる広大な信仰空間「奈良山」の神と、その従者である「おに」を祀るために建てられた」ということがわかります。そこには鬼北の「おに」、つまり祖先の霊・山の神の信仰が垣間見え、心のよりどころ、祈りの対象として今日まで語り継がれてきたのでしょう。
(注)鎌倉時代に原型ができた軍記物語で、日本三大仇討ちのひとつ。南北朝時代には本になり、江戸時代には歌舞伎や浄瑠璃などで演じられた。

国史跡等妙寺旧境内の近年の発掘調査等により、かつて等妙寺は「奈良山信仰の拠点寺院」として営まれたことが裏付けられてきました。
また、周辺の山中では山岳信仰・霊場遺跡の発見が相次いでおり、等妙寺旧境内はまさに日本古来の山岳信仰由来の「おに」=鬼北の「おに」を象徴する歴史遺産といえます。

鬼北の「鬼(おに)」伝説
鬼北地域に伝わる、「鬼(おに)」伝説をいくつかご紹介します。

- 「鬼ヶ城」という山(現在の松野町に位置する古鬼ヶ城山)は、「鬼王 段三郎」が大岩を引き寄せて造った「鬼(おに)」の城と伝わる。
- 等妙寺をどこに建てようか探していた理玉和尚の目の前に「鬼王」が突然現れ、大岩を軽々と投げ飛ばし、建立に適した場所を示したという。
- 鬼ヶ城山系の山中にある「タモト岩」と呼ばれる大岩は、「鬼王」の懐から落ちたという。
- 松野町の滑床渓谷にある「鼓岩」と呼ばれる大岩を「鬼王 段三郎」やその主君、曽我兄弟が力試しで動かしたとの伝承がある。