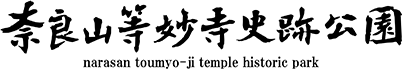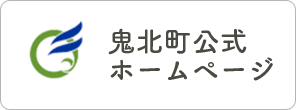本文
等妙寺旧境内の見どころ
等妙寺旧境内は今からおよそ700年前の鎌倉時代末、日本天台宗を開いた最澄の教えを広め、乱れた世を仏の道で導くため創建された山寺跡です。
学問を修め、厳しい修業を積んだ僧に戒師(かいし)の資格を与えることができる南国唯一の寺でした。
現地は発掘調査を経ながら整備が進み、歴史探訪や森林浴、ウォーキングなど憩いの場として気軽に立ち寄ることができる史跡公園になりました。
それぞれの見どころでは、かつての等妙寺がいかに栄えていたか、当時の面影を偲ぶことができます。
馬洗いの淵
「等妙寺縁起」によると、寺の建立地を探していた理玉和尚は、黒毛の馬を洗う曽我兄弟に出会ったといいます。
この場所は、そのシーンを彷彿とさせます。
清水谷旧参道
神聖な空気ただよう杉木立の中、沢のせせらぎが心地よい。
森林浴を楽しみながら、ゆったり歩こう。
旧参道の護岸石積み

谷川沿いの参道を造るとき、大きな石を積んで護岸を補強した様子が見て取れます。
カゴ池の石積み

カゴ池の堤。石積みの大部分は江戸時代から現代にかけて改修されたものです。
上部の薄く平らな横長石を低く積んだ部分が、中世の時代のものです。
福寿院跡
最も北側に位置する単独の平坦部。
風呂の焚き口とみられる遺構があります。当時の入浴方法は、蒸気を浴びる蒸し風呂(サウナ)のようなものでした。
石橋遺構
参道に連続して架けられた橋の一部です。
この橋を渡ると「常寂光土(じょうじゃっこうど)」という神仏の世界とされていました。
古の石段
この石段は、当時オリジナルのものです。
中央地区の小院群

見学ルート左手には、11箇所の平坦部が連続的に広がっており、所々に石積みも見られます。
雁木遺構(石の階段)
平坦部3から山中へ向かって築かれた重厚な石階段。
修行僧たちは、この石階段を登って山の神がいる修行場へと入っていきました。
展望場

見学ルートを登り切ったところにある絶景スポット。ひと休みしながら、全身で風を感じよう。
如意顕院跡

本堂や本坊、庭園跡などが見つかった中世等妙寺の中枢部。
最も重要な場は本坊客殿で、「重授戒灌頂(じゅうじゅかいかんじょう)」という特別な儀式が執り行われました。
本坊の石積み
中世期では最大規模・最高水準の技術で構築された石積み。
ほんぼうのい本坊の石積みは高さ6m、長さ25mあり、史跡内最大です。